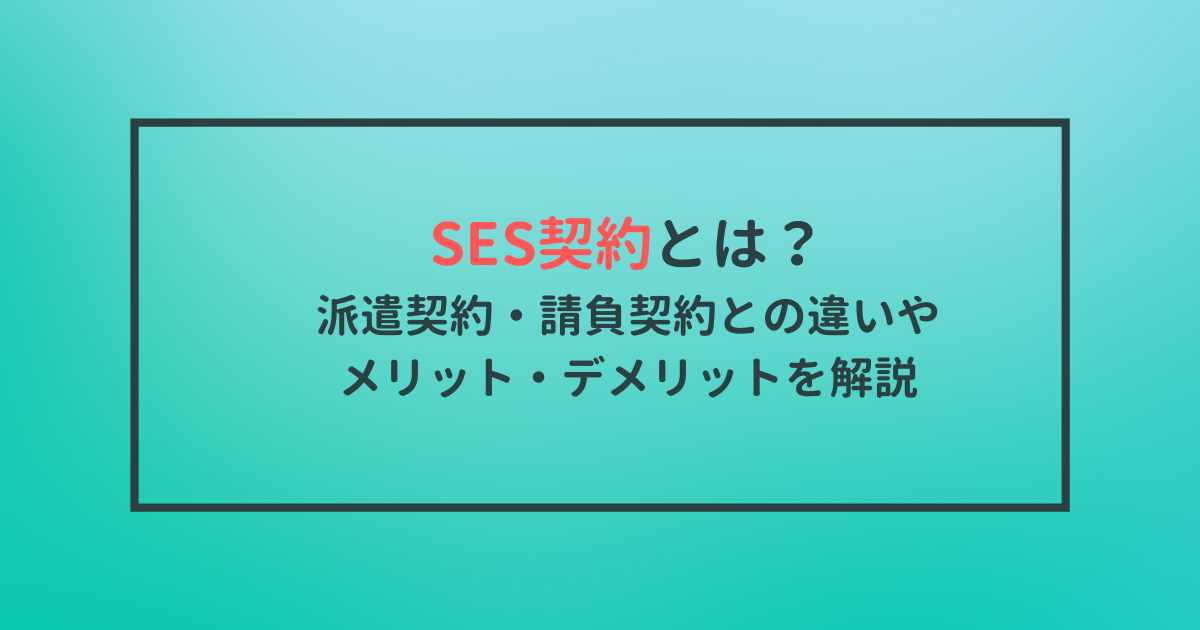
「SES契約ってなに?」「派遣契約や請負契約とどう違うの?」と疑問に思っていませんか。
SES契約とはIT業界でのみ使われる言葉で、準委任契約としてエンジニアの労働を提供するサービスです。
本記事では、SES契約の概要やほかの契約形態との違い、メリット・デメリットについて解説します。
アプリ・システム開発のプロが開発のお悩みを解決します

アプリ・システム開発の6割が失敗すると言われています。クライアントのリピート率100%のリレイスにご相談ください。
\ まずは無料相談!1営業日以内に返信 /
目次
SES契約とは
SES契約とはシステム・エンジニア・サービスの略称でIT業界で使われる契約形態です。
書面ではSES契約とは表さず、「準委任契約」という雇用形態で契約を交わします。
成果物に対する報酬ではなく労働力の提供に対する報酬が支払われ、クライアントのシステム・ソフトウェア開発やインフラ環境構築を行うために常駐してIT技術のサービスを提供します。
指揮命令権は所属している自社にあり、常駐先であるクライアントが指揮命令することはできません。
システムの運用や保守のためにSES契約が用いられるケースが多いです。
契約形態の種類
SES契約の理解を深めるためには、契約形態の種類について知っておくべきです。
派遣契約と請負契約について解説します。
SES契約と派遣契約の違い
そもそも派遣契約とは、派遣会社から派遣された企業で労働する雇用形態のことです。
業務内容は、派遣先の企業から定められ、その労働に従事しなければなりません。
そのため、依頼されたものを完成させる義務はなく、労働したことへの対価が支払われます。
SES契約と派遣契約の大きな違いは、指揮命令権です。
SES契約をしたエンジニアの指揮命令権は自社にありますが、派遣契約をしたエンジニアの指揮命令権は派遣先の企業にあります。
派遣先企業から直接指示を受けながら労働をします。
SES契約と請負契約の違い
請負契約とは、受託する業務を完了させることを約束し、発注者は完成物に対して報酬を支払う契約のことです。
もし納品した仕事にミスや欠陥があった場合、改修・修繕をしなければなりません。
SES契約と請負契約の大きな違いは、約束の内容です。
SES契約は依頼された期間に業務を行って技術を提供することを約束します。
一方、請負契約は決められた納期までに成果物を完成させなければなりません。
たとえば、「ゲームアプリの開発」の請負契約を締結したら、ゲームアプリの開発を終わらせ完成したものを納品します。
しかし、SES契約の場合、ゲームアプリを一定期間開発するという技術力を提供するだけで約束を守れています。
その間に完成させる必要はありません。
クライアント側のSES契約のメリット・デメリット
クライアント側のSES契約のメリット・デメリットについて解説します。
クライアント側のSES契約のメリット
クライアント側のSES契約のメリットは、主に2つあります。
契約したエンジニアが常駐してくれる
SES契約によって正社員以外のエンジニアが自社に常駐してくれるため、常駐案件の発注がしやすいです。
外部のエンジニアのリソースを素早く確保できます。
ただし、雇用側に指揮命令権があることだけ忘れないよう注意しましょう。
一時的な人材確保が可能
ITシステムの会社では、抱える案件数や急なアップデート、トラブル対応などによって短期間だけエンジニアが必要となることが少なくありません。
常に正社員を抱えることはコスト的に厳しく、採用できるかどうかの不安要素が常に付き纏います。
エンジニアを突発的に期間限定で常駐させられるSESを活用するITシステム会社は多いです。
必要なときに必要な能力・スキルに応じた人材確保ができることは、大きな魅力と言えるでしょう。
クライアント側のSES契約のデメリット
クライアント側のSES契約のデメリットは、成果を保証する契約ではないことです。
SES契約は請負契約と違って、ITエンジニアの労働を約束する契約です。
そのため、工数の見込みが甘かったり、作業進捗が遅かったりすると完成されないまま契約期間が終了するかもしれません。
予想以上に時間や費用がかかる可能性もあります。
想定の期間内に望んだ成果が得られるとは限らないため、注意しましょう。
エンジニア側のSES契約のメリット・デメリット
エンジニア側のSES契約のメリット・デメリットについて解説します。
エンジニア側のSES契約のメリット
エンジニア側のSES契約のメリットは、主に2つあります。
様々な環境で経験を積むことができる
契約ごとに環境が変わるため、様々な経験が積めるメリットがあります。
業界や企業規模の違う職場を渡り歩けることは、とても貴重です。
独立したいと考えている人や、いずれどこかの会社で正社員で働きたいと考えている人にとっては、自分に合う職場探しのできるチャンスです。
正社員雇用の機会を探すことができる
クライアントによっては、希望があれば正社員の勧誘があります。
雇用契約を結ぶ前にSES契約で働いて会社のことを知ってから正社員になるチャンスがあるため、雇用されたあとにギャップを感じることが少ないです。
もし、正社員の勧誘がなくても、別の案件で呼んでもらえたり、所属する会社の評価があがったりするきっかけづくりができます。
エンジニア側のSES契約のデメリット
エンジニア側のSES契約のデメリットは、主に2つあります。
給料が安くなる
SES契約で働くエンジニアの給料は安い傾向です。
その理由は、IT業界における多重下請けの構造にあります。
たとえば、大企業が大きなプロジェクトを受けると、プロジェクトは工程ごとに細分化されて1次請け企業へ依頼されます。
そこから2次請け、3次請けと下請けに回され、企業へ入る利益はとても少ないです。
また、実際に手を動かすエンジニアへの給料は、基本的に時給単価で計算されます。
そもそもの時給が低く設定されているケースが多く、給料アップも難しいでしょう。
契約ごとに環境が変わる
契約ごとに職場が変わるため、都度新しい環境に慣れる必要があります。
多くのSES契約の期間は1〜3ヶ月程度です。
つまり、1〜3ヶ月ごとに職場が変わり、一緒に仕事する人も変わります。
仲良くなったり馴染んだりした頃に契約期間が終わってしまうため、ビジネスライクな付き合いになりやすいようです。
偽装請負に注意
SES契約を締結するときは、偽装請負に注意しましょう。
偽装請負について、詳しく解説します。
偽装請負とは
偽装請負とは、請負契約や準委任契約を結んでいるものの、実質は労働派遣や労働者共有をしていることを指します。
SES契約では、エンジニアをクライアント先に常駐させますが、クライアントからの直接指揮命令を出すことは禁止されています。
ただし、なかには指揮命令がクライアントから出ていることがあり、この状態は派遣契約と同じ状態です。
本来、派遣契約を締結するには、届出をして許可を取得しなければなりません。
しかし、ルールが厳しいため許可を取得できない事業者が派遣事業と同じことを行いたいがために、上部だけSES契約として締結することを偽装請負と言います。
無許可で人材派遣を行った場合、職業安定法違反とみなされます。
クライアントに悪気がなく、「指揮命令権はない」ことを知らなかったとしても偽装請負と認められることがあるため、十分に注意しましょう。
偽装請負で過酷な労働環境になる可能性も
偽装請負によって、過酷な労働環境になる可能性があります。
なぜなら、SES契約だとクライアントにはエンジニアを守る義務がなく、長時間労働や休日出勤を支持されることがあるからです。
SES契約には残業や深夜労働に対する決まりごとがなく、時間外の手当は発生しません。
いくら働いてもクライアントから支払われる報酬は変わらないため、低賃金労働を引き起こします。
また、偽装請負が発覚すると、労働局からの指導やペナルティを課せられることがあります。
企業は業務停止命令を受けることになり、エンジニアやほかの従業員は働く環境を失いかねません。
エンジニア自身がペナルティを受けるわけではありませんが、偽装請負を是正しないままだとデメリットを被る可能性があると理解しておきましょう。
まとめ
SES契約とは、クライアントの職場に常駐してエンジニアの労働を提供し、それに対して報酬を受け取る契約形態です。
指揮命令件は自社にあり、クライアントから支持されることは禁止されています。
成果物ではなく、エンジニアのリソースを提供しているため時給で支払われるケースがほとんどです。
幅広い業界や職場で働くことになるため、スキルアップに役立つでしょう。
SES契約をする際は偽装請負に注意し、エンジニアとしての経験値を高めましょう。

